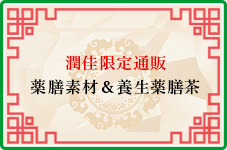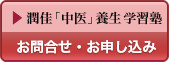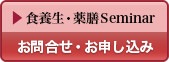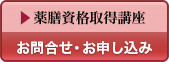HOME» Blog【食養生の豆知識】 »Blog~真夏の「中医学」食養生の豆知識(第2回)
Blog【食養生の豆知識】
Blog~真夏の「中医学」食養生の豆知識(第2回)
第2回 養生薬膳で猛暑や蒸し暑い時期を乗り越えましょう!
はじめに:
「中医学」食養生は天人合一や医食同源など考えのもとで健康維持(体調を整う)、病気予防(病後の食事療養)、更に延年益寿を図る飲食方法。
基本は季節気候や体調を考慮し、適切な食材(または薬膳食材)を選び、
その効能を活かして日々の食事に取り入れることは大事なポイントです!
ちなみに、養生薬膳とは養生するため膳食とのことで、初心者でも食材選びなどの知識を身につければ、手軽に実践出来るものと思います。
今年の夏はとても暑いと言われておりますが、みなさんと共に元気で、楽しい夏を過ごしたいと思いますので、少しでも参考になれば、嬉しいです♪
一、真夏の季節特徴と現われやすい不調
A 夏の季節特徴:
夏の季節とは 暦上では 5月始めの「立夏」~7月の20日ごろ「立秋」までの3ヶ月間を指す。
(実際は 中間の6月10日前後~7月の20日ごろの40日間は梅雨の時期を含む。)
初夏は爽やかで、過ごしやすいのですが、
後半は真夏で、今の時期の蒸し暑い時期や梅雨あけてから更に猛暑見舞われる時期と思われますね。
一年の中、最も気温高い季節で陽気も最も旺盛な時期になります。
動植物は 生長、繁栄の時期。
人間は 陽気の影響を受けて、エネルギー満ちて、積極的活動する時期。
自然の「五行」からみる:
火~ 夏~ 暑~ 長~ 南~ 赤~ 苦~
夏~ 「火行」に
特徴は、“炎上”「a温熱; b上昇(昇騰)」性質をもつ
真夏の度合いが超える暑さや猛暑の場合は 「中医学」では暑邪として捉えて、
身体に不調を引き起こす原因に!
暑邪の特性:
①「炎熱」の特徴
②「升散」の特徴
③「傷津耗気」の特徴
④「陽邪」で陰液を損傷しやすい
B 真夏の高温・猛暑時期に
~暑邪による身体の不調
「炎熱」→ 身体が熱を帯びやすく
~ 体温上昇など (ひどくなると、口内炎; 鼻血。など)
「升散」→ 上半身に熱しやすく
~のぼせ、頭がぼーとする; 発汗。
「傷津耗気」→体内の水分消耗(汗かなど)による気も消耗されて
~疲れが出やすい。
「陽邪」で陰液を損傷しやすい →身体の水分が消耗され
~口渇、尿濃いなど
※ 蒸し暑く高温多湿の場合:
~「暑邪+湿邪」による不調(暑邪の不調と湿邪の不調を合さる)
顕著なのは:湿邪で→気の巡りが悪く、更に体内に熱が籠もりやすい。
「湿熱証」~①身体が熱籠もり、 頭重い;
②(汗はスッキリ出ない; 口粘々しやすい。)
③ 脾胃の気滞を招きやすく、膨満感; 胸悶、吐き気
④ 四肢が重だるい; 又は むくみなど
C 夏バテの主な症状:
|
高温(暑邪)による症状 |
高温多湿(暑邪+湿邪)による症状 ◆ 身体に熱が籠もる;頭ぼーとする、頭重 |
※夏バテになりやすい人:
・乳幼児、高齢者
・虚弱体質、胃腸が弱い人(心臓の弱い人も)
・環境、気候の変化に過敏に反応する
二、食養生対策
A 「暑さ(暑邪)への対策」
1,体内の熱(ほてりや体温に上昇など)
「清熱解暑」 身体の熱を取る~ 夏野菜、果物など
(炎症があるとき「清熱解毒」身体の熱毒を取る~ 苦味、鹹味など
2,喉の渇きなど体内水分(津液)不足
⇒「生津止渇」体内の水分増やし余熱を冷ます~夏の果物、野菜など
3,体内水分の喪失(傷津)による気の消耗、疲れ
⇒「補気摂津」気を補う ~穀物、芋類など
※汗が多い時には ⇒ 「酸味の物」を加え、収斂させる
B「高温 多湿(暑邪+湿邪)への対策」
1,湿熱の邪で熱が籠もり、頭がボーとするなど
⇒ 「清熱利湿」 身体の上の湿邪をとる~例えば 苦瓜、麦茶など
2,湿熱の邪で、脾胃の不調など
⇒ 「芳香化湿」 中焦の‘湿邪を取る ~ハーブや香辛料など
3,湿熱の邪で重だるい; むくみなど
⇒「清熱利水」利水による体内水分代謝をよくする~豆類や鳩麦など
2016/07/14

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)